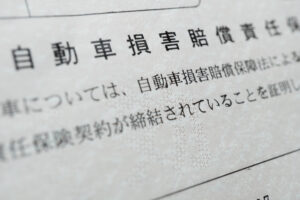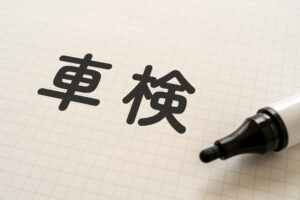「自賠責って何のための保険?」
「加入する方法は?」
今回は、自動車(車、バイク、原付)を所有、運転するときに必ず加入しなければいけない”自賠責保険“について目的や加入方法など知っておいたほうがいい知識を徹底解説します!
何かあったときの為の保険というイメージで軽く考えているかもしれません。しかし、自賠責は必須であり、取り返しのつかない事態が発生するかもしれません。
この記事を参考に自賠責への理解を進めてください。
自賠責保険とは?前提となる基礎知識について
まずは基礎となる情報からご紹介します。
自動車の保険について
自動車に関する保険は、相手方への損害賠償を保証するための自賠責保険(強制保険)と、自賠責では保証しきれない損害を補償する自分の意志で加入するか決める任意保険が存在します。
自賠責保険とは?
”自賠責”とは、日本における法で定められた自動車保険で、正式名称は”自動車損害賠償責任保険”といいます。この保険は自動車(車、バイク、原付)を運転または所有するものが人身事故によって、他人に対して与えた傷害や死亡、財産に対する損害の賠償責任をカバーする為のもので、すべてのドライバーが加入しなければいけない強制保険です。
未加入時の罰則について
自賠責保険未加入での運行は法律違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数6点が科され免許停止の可能性があります。
(自賠法第86条の3、道路交通法第103条、第108条の33)
自賠責保険と任意保険の違いについて
自賠責保険は、車の所有や運転するにあたって加入が強制されており、被害者に対しての補償がメインの保険です。 しかし、任意保険は加入が強制されておらず、事故をしたときに自賠責保険ではカバーしきれないことに対しての保険となるため、万が一の備えとしての保険です。
任意保険に未加入で、相手の車の賠償金でトラブルになることも考えられるため、加入をオススメします。
任意保険については、自動車保険を取り扱う損保会社に問い合わせてみてください。
自賠責保険の補償範囲について
自賠責保険での補償内容については、幅広く障害・後遺障害による損害・死亡による損害など多岐に渡り、また条件などもあります。
今回の記事では自賠責保険の基礎となる部分に重点を置き、補償範囲や保険金請求時の流れについては別記事で紹介いたします!(7月3日:未更新)
自賠責保険の料金、契約期間について
自賠責保険に加入するには手続きが必要となります。
初めての加入でなくても自賠責保険には契約期間や契約する自動車によって保険料が異なってくるため注意して加入手続きをしなければいけません。
保険料金と契約期間を説明 していきます。
保険料金と契約期間
金額は、車種それぞれの期間で異なってきます。車種と期間の保険料は以下の表を参考にしてください。
| 分類番号 | 車種 | 60か月 | 48か月 | 37か月 | 36か月 | 25か月 | 24か月 | 13か月 | 12か月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・5・7 | 自家用乗用自動車 | ー | ー | 24,190円 | 23,690円 | 18,160円 | 17,650円 | 12,010円 | 11,500円 | ||
| (軽)4・5 (6・8) | 軽自動車(検査対象車) | ー | ー | 24,010円 | 23,520円 | 18,040円 | 17,540円 | 11,950円 | 11,440円 | ||
| 4 | 小型貨物自動車 | 営業用 | ー | ー | ー | ー | 27,090円 | 26,240円 | 16,700円 | 15,830円 | |
| 自家用 | ー | ー | ー | ー | 20,950円 | 20,340円 | 13,480円 | 12,850円 | |||
| 1 | 普通 貨物 自動車 | 営業用 | 2t超 | ー | ー | ー | ー | 44,130円 | 42,610円 | 25,640円 | 24,100円 |
| 2t以下 | ー | ー | ー | ー | 31,120円 | 30,110円 | 18,810円 | 17,790円 | |||
| 自家用 | 2t超 | ー | ー | ー | ー | 32,030円 | 30,980円 | 19,290円 | 18,230円 | ||
| 2t以下 | ー | ー | ー | ー | 29,300円 | 28,370円 | 17,860円 | 16,900円 | |||

二輪車、バス、大型・小型特殊自動車は各種サイトをご確認ください。
新車購入時は36か月、2回目の車検以降は24ヶ月など車検周期に合わせることで契約忘れを防ぐことができ、長期契約を選ぶと1か月あたりの保険料が安くなるのでお勧めです!
25か月の契約期間とは
契約期間には、車検の有効期限とのズレを考慮した25か月という契約期間が存在します。
車検の有効期限は満了日の24時までですが、自賠責の有効期限は満了日の12時であり、無保険状態を避けれるように25か月に加入するものです(13か月、36か月についても同様です)。
また、自賠責保険はどの会社で手続きをしても金額が変わらないので、どこで契約しても金額は一律です。
手続き可能な場所、流れについて


手続きは主に以下の場所で行うことができます。
- 車、バイクのディーラーや販売店
- 損害保険会社
- 保険代理店
- ガソリンスタンド
(125cc超え250cc以下のバイクや原付は郵便局、コンビニ、インターネットでの加入が可能です。)
販売店で購入と同時に加入手続きをしてもらうのが、一般的であり一番楽で分かりやすいと思います。
各場所での手続きの流れ
各場所での基本的な流れを紹介していきたいと思います。
手続きは簡単ですが、場所によって異なる場合があるので、事前に手続きをしたい場所を調べることをオススメします。
車、バイクのディーラーや販売店
車を購入すれば自賠責保険に加入しなければいけないため、購入と同時に加入する流れが一般的な流れです。
購入時の様々な手続きの中で、自賠責保険の加入の手続きがあるので簡単に流れで手続きができます。
損害保険会社
損害保険会社の営業所や支店窓口にて、必要事項を契約書類に記入し、保険会社に提出します。そして、保険料を支払うことで、自賠責保険証書を受け取り手続き完了です。
損害保険会社では、その他の名義変更、再発行、契約内容の変更などもできます。
保険代理店
代理店に自賠責保険の加入について相談し、必要事項を契約書類に記入し提出をして、保険料を支払うことで自賠責保険証書を受け取り手続き完了です。
損害保険会社と同じ流れなので分かりやすいと思います。
ガソリンスタンド
ガソリンスタンドでも、保険会社や代理店と同じ流れで手続きすることが可能ですが、即日加入に対応していないことが多いので、ガソリンスタンドで手続きをする際は事前に確認するなど注意して手続きを行ってください。
125cc超え250cc以下のバイクや原付
125cc超え250cc以下のバイクや原付は郵便局、コンビニ、インターネットで手続きできます。郵便、インターネットでの手続きを行う場合は、保険開始日が自賠責保険証書を受け取ってからなので、手続きをしたから運転していいわけではないので注意しましょう。 コンビニではマルチコピー機やLoppiで必要事項を記入し、申込券を発行し、レジで保険料を払うことで自賠責保険証書を受け取り完了です。
手続きに必要なものについて
手続きの際に必要になってくる書類を事前に準備しなければなりません。
忘れ物のないよう気をつけて確認していきましょう。
自動車の情報が分かるもの
自動車の車台番号や登録番号などの情報が分かる書類が必要です。基本的には車検証などが一般的です。
車検のない原付は、標識交付証明書、小型バイクでは軽自動車届出済を用意します。
保険契約者の本人確認書類
本人確認ができる運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどのコピーが必要になる可能性があるので準備しておきましょう。
保険料
保険料が支払えないと手続きが完了しません。先ほどの保険料の表をしっかり確認して、保険料を忘れないようにしましょう。
その他
印鑑(法人の場合法人印)が場所によって必要な場合もあるので確認をしてから手続きを行いましょう。 また、更新の手続きの場合は現在の自賠責保険証明書も忘れずに持っていくようにしましょう。
まとめ
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、車を保持するにあたり必要な保険で、法律で定められた絶対に入らなければいけない強制保険です。未加入、未更新だった場合は捕まってしまいます。
楽しいカーライフを過ごすためにも、ここで得た知識を活かし事前に確認や準備をして運転に挑むようにしましょう。